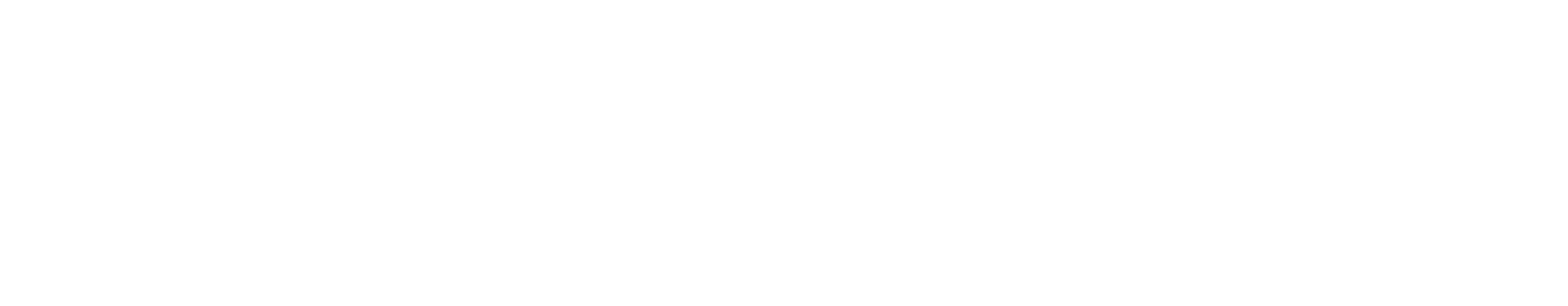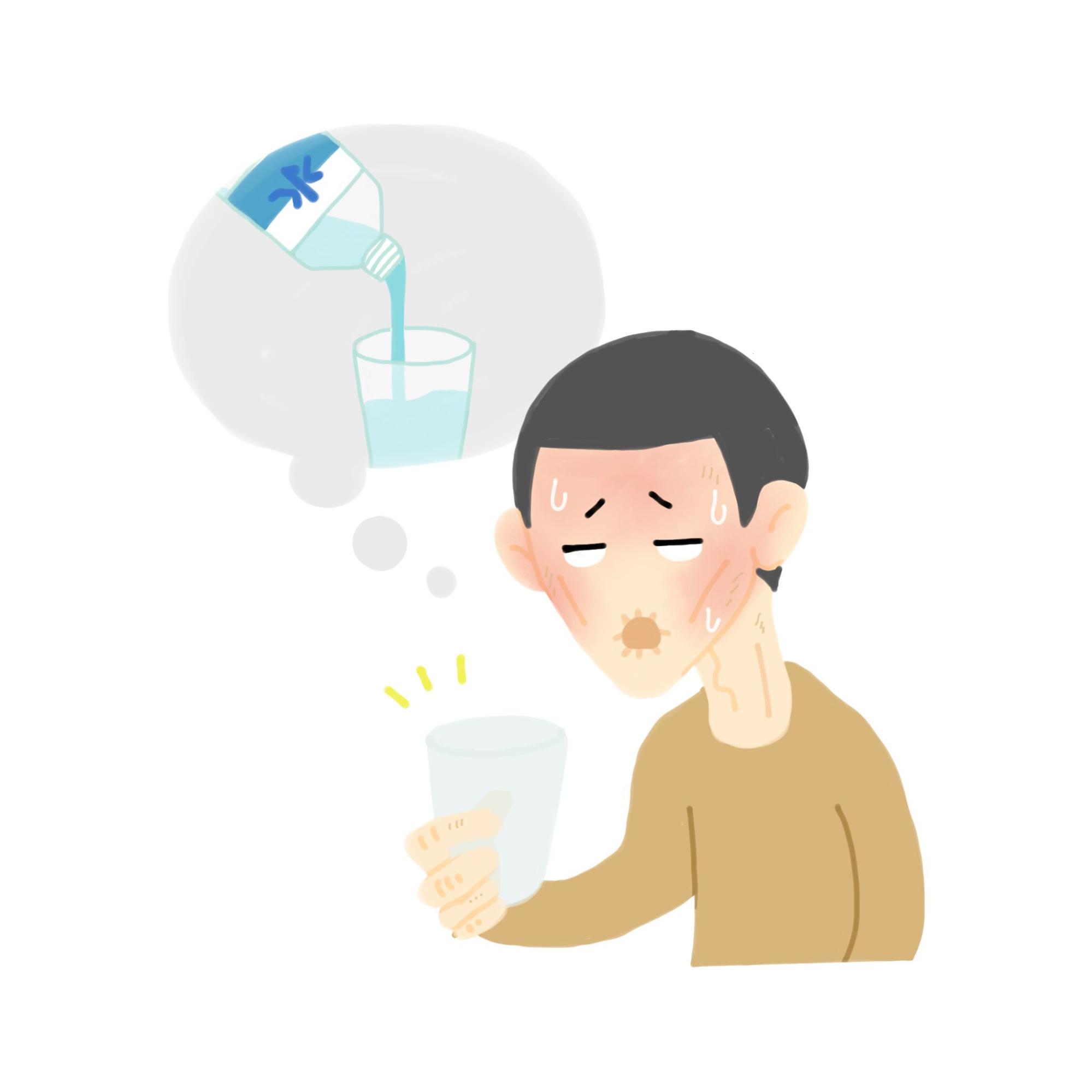こんにちは♪成宮です♪
今月は今日で営業終了です!!
4月からまたよろしくお願いいたします。
4月休業日は15日です♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
便秘について
便秘になる原因
便秘の原因は人によってさまざまですが、食事や運動、生活習慣の影響によって慢性的な便秘が引き起こされることがあります。
ここでは、便秘になる7つの原因と対処法を紹介します。
ストレス

腸の働きとストレスは一見関係のないように思えますが、便秘の原因の多くはストレスによるものと言われています。
消化した食べ物を腸の中で動かしたり排出したりする腸管のぜん動運動は、自律神経である交感神経と副交感神経のバランスによって保たれています。
しかしストレスが溜まると交感神経が優位になり、動きが停滞してしまいます。
それにより、排便習慣のリズムが乱れ便秘を引き起こしてしまうのです。
日常生活の中では人間関係の問題、仕事でのトラブル、生活環境の変化などがストレスにつながりやすいと言われています。
また、完璧主義、せっかちなどの性格によってストレスが溜まることも多くあるので、体を動かしたり、ゆっくりと湯船につかったり、趣味や好きなことを楽しむ時間を作ったりするなど、うまくストレスを発散し、副交感神経を優位にするよう心がけましょう。
運動不足による筋力不足

腸のぜん動運動は、運動不足により筋力が衰えることによっても動きが鈍くなります。
その結果、筋力不足が原因で腹筋の力が弱くなり、便意を感じても上手く排便できなくなるケースもあるのです。
「デスクワークで長時間座っている」「少しの距離でも車に乗ることが多い」など、日常的に運動量が少ない人は筋力不足が便秘を引き起こしている可能性があります。
このような場合は、腹筋を鍛えるトレーニングを習慣にすることがおすすめです。
ウォーキング・ジョギング・ヨガなどの全身運動も腹筋を刺激するため、腹筋運動と併せて行う事で便秘改善に役立つでしょう。
過度なダイエット

腸内にはある程度の便がないと便を押し出すことができず、排便が難しくなります。
過度な食事制限ダイエットで食べる量を減らしてしまうと、栄養が偏ってしまい、食物繊維の摂取量が減ります。
その結果、便のカサと水分量が減少し、便自体の量が減ってしまうのです。
また、ダイエット中は脂質を制限することがありますが、脂質は便の滑りを良くする作用があります。
さらに、脂質に含まれる脂肪酸は大腸を刺激してぜん動運動を促進する効果が期待できるため、適度な脂質の摂取が便秘解消に役立ちます。
体に必要な栄養が不足すると血行不良や自律神経の乱れを引き起こして腸の働きを悪くすることがあるので、身体に負担がかかり過ぎるようなダイエットは避け、バランスの良い食事を摂りましょう。
食生活の乱れ

肉ばかり食べたり野菜が不足したりするなど、食生活の乱れも便秘を引き起こす原因です。
肉類に含まれる動物性タンパク質は、過剰に摂りすぎると悪玉菌のエサになって腸内環境を悪化させることがあります。
また、野菜には、消化吸収されずに大腸まで届く水溶性食物繊維・不溶性食物繊維が含まれており、それぞれの食物繊維には便秘解消につながる特徴があります。
したがって、適度に野菜を摂取することが必要となるのです。
【水溶性食物繊維】
水に溶けてゲル状になる性質があり、便を柔らかくして排便を促す効果が期待できます。
【不溶性食物繊維】
水に溶けにくい性質があり、水分を吸収して膨らむことで腸のぜん動運動を促したり、便のカサを増やしたりして、排便を促す効果が期待できます。
【食物繊維が多い食べ物】
・穀物:玄米ごはん・ライ麦パン・オートミールなど
・海藻類:わかめ・ひじき・めかぶなど
・芋類:さつまいも・こんにゃく・山芋など
・きのこ類:きくらげ・干ししいたけ・なめこなど
・ドライフルーツ:柿・ブルーベリー・なつめ・いちじくなど
・豆類:納豆・あずき・いんげん豆など
水分不足
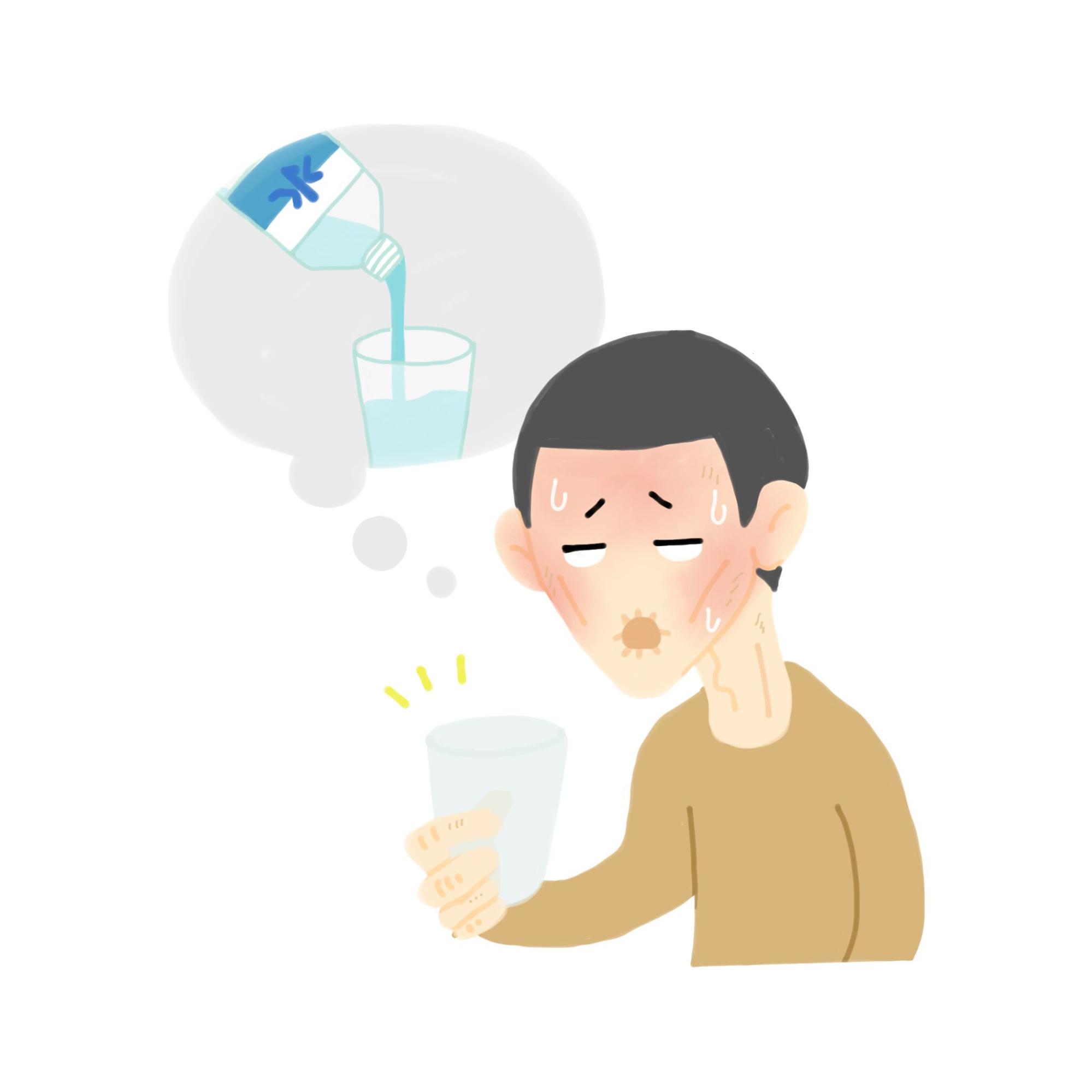
便は約75%が水分、残りの25%が食物繊維を含んだ食べ物のカスと腸から脱落した腸内細菌の死骸などの固形成分です。
便は水分を含んでいるからこそ、容積が膨らみ、大腸内を移動しやすい硬さとなります。
そのため、水分不足になると便の水分量が減り、カチカチの硬い便となって排出しにくくなってしまいます。
日常的に水を飲む機会が少ない人は、水分不足が便秘を引き起こしている可能性があります。
1日の水分の摂取量目安は2.5リットル(内訳:食事から1リットル、飲料水から1.2リットル、体内で作られる水0.3リットル)とされており、1日かけてこまめに水分を補給するようにしましょう。
福岡県北九州市小倉北区京町4-4-38
男女兼用サロン・現金払い
深夜営業・プライベート空間
代表 成宮 瑞季